【現場を変えるMobilityのアイデア】第34話:iPad導入を成功へと導く用途と運用の両輪

福田 弘徳
株式会社Too モビリティ・エバンジェリスト
企業や教育機関向けのApple製品の活用提案や導入・運用構築を手がける株式会社Tooのモビリティ・エバンジェリスト。
www.too.com
「クリエイティビティを解き放とう」。アップルのWEBサイト「アップルと教育」の最初に出てくるメッセージである。今春シカゴで行われたアップルのイベントは教育市場にフォーカスした内容で、教育向けの新しいプログラムが続々と発表された。その中のひとつ「Everyone Can Create」は、すべての科目にクリエイティブな表現を取り入れるための新しいカリキュラムで、この秋にリリース予定である。
日本の教育現場でもICT化の促進やプログラミング的思考の習得など、学習スタイルに変革が求められている。クリエイティビティは、これからの社会を生き抜くための重要なスキルであり、それをいかに育てるかがこれからの教育現場でもっとも大事なことではないかと思う。
ビジネスの現場でも重要視されている能力のひとつであるクリエイティビティは、イノベーションを起こすために必要な要素とされている。しかし、クリエイティビティとは何か?と考えてみると、しっかりとした定義がなく、非常に曖昧なスキルという印象ではないだろうか。
日本語に翻訳すると、創造性や独創性といった言葉に置き換えられるが、具体的にどのようなスキルなのかわかりにくい。人によってさまざまな解釈があり、抽象度の高い言葉である。映画やアニメーション、話題の広告メディアなど、一流のクリエイターが持っている生まれ 持ったスキルという印象もあるが、私は違うと思う。クリエイティビティは、「問いを立てる力」だ。
問題解決能力は社会を生き抜く術として重要とされる。しかし、立てた問い次第で導き出される答えは変わるので、間違った課題設定をしてしまえば、正しい答えを導き出すことはできない。問いを立てる力、つまり課題設定の始まりは、「なぜ気づかなかったのだろう」という当たり前のことを、他の人よりも先に気づくことである。
課題とは、理想と現実のギャップから生まれるものだ。どうやって理想を描くかを考え始めると、何よりも自分自身の体験がきっかけとして必要になる。こうありたいと思う環境を作ること、その環境で得る体験こそが理想と現実のギャップを可視化する。教育現場におけるiPad導入やスウィフト・プレイグラウンド(Swift Playgrounds)のようなプログラミング学習のツールなども、そういった体験環境を作ることを目指したものでなければならない。
また、インターネットで必要な情報が何かを検索するうえでも、検索結果を読み解くうえでも、「問いを立てる力」は必要だ。教育機関の中にはiPadに機能制限やコンテンツフィルタリングをかけ、子どもたちのインターネット利用を制限しているところも多い。だが、子どもたちに情報リテラシーを身につけてもらい、新しいことを学ぶ意欲や好奇心を持ってもらいたいなら、iPadの機能制限は最低限であることが望ましい。
教育現場のICT化の本質はタブレット導入でもデジタル教科書でもない。テクノロジーを利用する目的は、あくまで「問いを立てる力」を身につけることを補助するためのものだ。プログラミング的思考をカリキュラムに盛り込むのも、問題解決の手法のひとつを学ぶことに過ぎない。
子どもたちの「問いを立てる力」を養うことこそが教育現場で重要なことであり、同時にクリエイティビティを育むことが問いの可能性を広げ、社会のさまざまな問題を解決し、変革を起こす原動力となる。iPadの活用やプログラミング的思考のようなテクノロジーを活用するのは、問いを考えるプロセスを楽しむため。まずは、そこから始めよう。
この記事は、Mac Fan連載「現場を変えるMobilityのアイデア」の転載です(初出:Mac Fan 2016年11月号)。
現場を変えるMobilityのアイデア 記事一覧
- 第34話:iPad導入を成功へと導く用途と運用の両輪
- 第33話:Apple ID管理の「解」来たる!?
- 第32話:可能性を拡張する問いを立てる力
- 第31話:腹落ち感が生み出す研修の価値
- 第30話:モバイル活用の本質を見直すタイムマネジメント
- 第29話:結果につなげる 「×考え方」のビジネス方程式
- 第28話:CXを高めるApple製品の客室導入
- 第27話:不快を味わい「学び」をアップデート
- 第26話:CYODの実現に最初に必要な Why? の問い
- 第25話:他社を真似ずに自分たちで“事例”は作る
- 第24話:「ソリューション」という幻想に惑わされない秘訣
- 第23話:AI時代のエコシステムと価値創造に必要な対等な“ツッコミ”
- 第22話:“デジタル変革”に もっとも大切な 目的の明確化と共有
- 第21話:企業の体質改善に求められるITの"目利き力"
- 第20話:心地良さの追求がIT機器導入を「変革」へと導く
- 第19話:iOSによる教育現場の化学反応
- 第18話:企業カルチャーを創り出すオフィスとiOS
- 第17話:知的好奇心を刺激する学び
- 第16話:ITサポートに求められるのは"寄り添う"姿勢
- 第15話:創造力を守るための時間確保
- 第14話:日本のEnterprise ITに足りないもの
- 第13話:形骸化させない"働き方"改革
- 第12話:志は高く、目線は低く、ユーザー視点で
- 第11話:幸せを呼び込むタスク管理
- 第10話:変化するのは人か、 テクノロジーか、 それとも…?
- 第9話:モビリティの成功の秘訣は「型」にあり
- 第8話:ムダな会議を撲滅、 有意義な時間を創出
- 第7話:教育現場でのiPad機能制限、絶対反対!
- 第6話:モビリティの三段活用
- 第5話:悪いルーティーンを打破するiOS
- 第4話:そのプレゼンは聴く者を動かしているか?
- 第3話:情報共有はInformationからKnowledgeへ
- 第2話:目的の定まった"定着する"モバイルの活用
- 第1話:そのマニュアルは使われているか?
関連記事

【現場を変えるMobilityのアイデア】第34話:iPad導入を成功へと導く用途と運用の両輪
2026.01.16

過去と未来が交差する展覧会「昭和100年パッケージ プロのデザイナーが考える、もしも昭和が続いていたら?」
2025.12.25

空間デザインの最前線を示す。日本空間デザイン賞2025 KUKAN OF THE YEAR が決定
2025.12.11
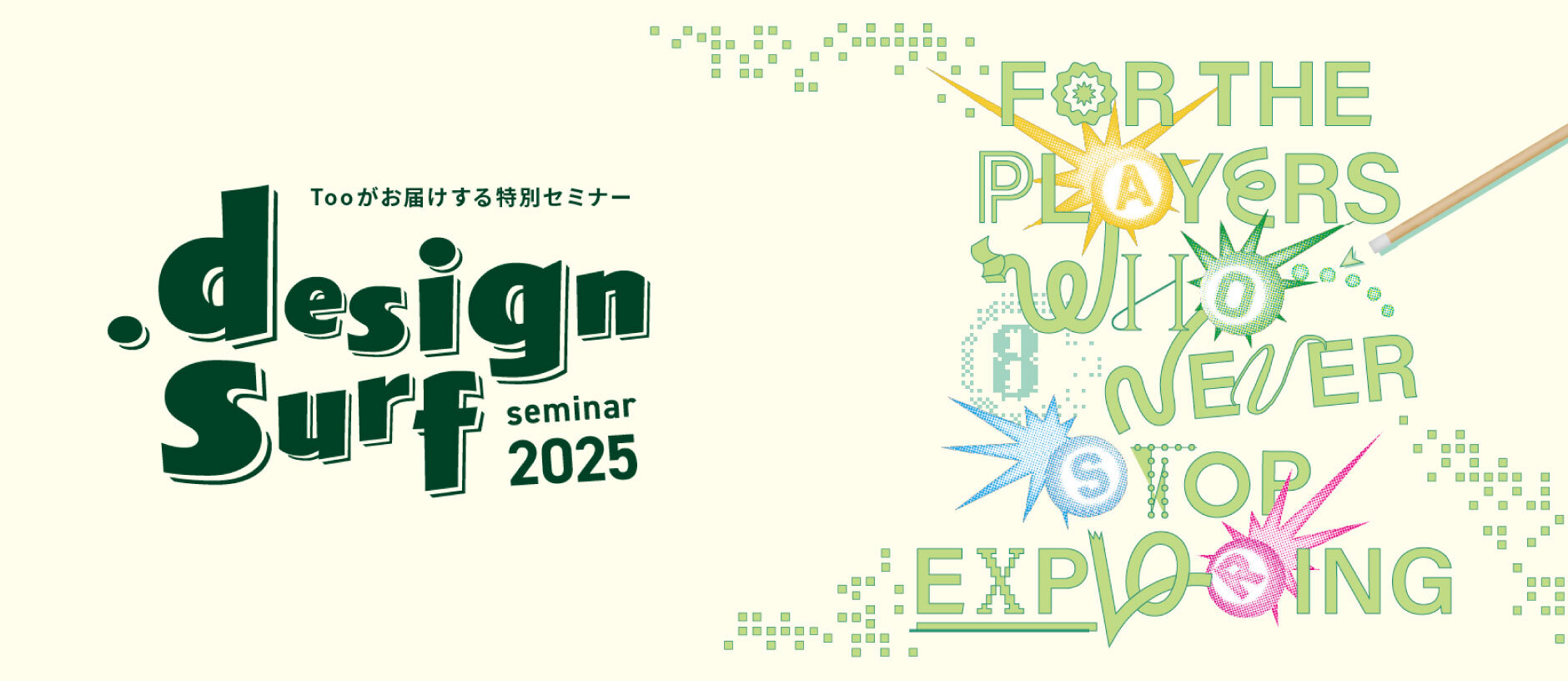
【design surf seminar 2025】design surf seminar 2025 速報
2025.11.10

【現場を変えるMobilityのアイデア】第33話:Apple ID管理の「解」来たる!?
2025.10.27

Designship 2025が開催。デザインと共に歩むパートナーシップの姿勢を発信
2025.10.15

実りの秋に収穫する、最新デザインとビジネスの知見 - design surf seminar 2025 見どころ紹介
2025.09.25










