【現場を変えるMobilityのアイデア】第34話:iPad導入を成功へと導く用途と運用の両輪
2021年に創立60周年を迎えた一般社団法人日本商環境デザイン協会(JCD)様。節目の年を記念して、「空間とアートのフュージョン」と題したトークイベントがJCD関東支部様の主催で2022年6月17日(金)に開催されました。五反田にある東京デザインセンターで行われた当日のイベントの様子をレポートします。
このイベントには、インテリアデザイナーのグエナエル・ニコラ氏と、アートコーディネーションなどを手がける藤田あかね氏がモデレーターとして参加。4名のアーティスト、平面作品の岡林里依氏、はやしまりこ氏、デジタル作品を手がける木之内憲子氏、彫刻家のKAARA氏が登壇し、空間におけるアートの見解を引き出していきました。
インテリアデザイナーや建築家が会員の多くを占めるJCDでは、アーティストを「空間におけるエレメントのクリエーター」と捉え、アーティストの活動と同時にインテリアデザインを底上げする活動を進めていきたいという、理事長 窪田茂氏と、事業部長 大滝道晴氏によるメッセージからイベントが始まりました。
今回のトークイベントに合わせ、会場にはそれぞれのアーティストがこの日のために制作した1日限りのインスタレーションが展示されました。テーマは「FLY」。アーティストから、映像、彫刻、絵画それぞれの作品の紹介がされました。
人々の心に寄り添う空間の中のアート
一つ目のトークテーマとして、ニコラ氏から「空間の中のアートの目的は何か?」という質問が投げかけられました。
木之内氏からは美しさという機能、空間を表現するためのメディアを兼ね備えた「魔法の装置」と回答が。明らかなロジックで説明できない点が、デザインとはまた異なる意味合いを空間にもたらすと述べました。
はやし氏は、人の気持ちを表現すると回答。例えばインテリアデザイナーが設計した空間にアートを入れると、感情に訴えかけるという点で重要だと話します。その中ではやし氏は特に、「自然のエネルギーを表現する」ことを大切にしていると語りました。
岡林氏は、クライアント、建築家や空間デザイナーの想いや考えを直接会って対話を重ねることで作品をイメージしやすくなり、その空間からしか生まれない作品を描けるようになると語ります。
KAARA氏は、アートは文学に似ていると述べました。常にその空間に存在し、開かなくても問題ないが、好きなときに開ける状態にある。その日の気分によって、安らぎになったり刺激になったり、自分のパッションを呼び覚まされるきっかけになる存在だと語ります。作品を見るたびに異なる意味を見出すような、その空間にいる人の心に寄り添った存在であるように心がけているそうです。
モデレーターの藤田氏もこの話を受けて、アートは空間の光や気温、そして人々の経験値や感覚によって違う見え方をするからこそ、感情に結びつきやすいと語ります。ニコラ氏も「このアートも1時間前と見え方が変わっている」と、4人のインスタレーションを指して述べ、自分の心の変化と共に見え方が変わっていくアートは非常に良いとまとめました。
プロジェクトの完成に不可欠なコミュニケーション
続いてのトークテーマは、「プロジェクトの依頼を受けたときにどのような情報があるとやりやすいですか?」という内容です。会場にいる多くのインテリアデザイナーからも同感の声が聞こえました。

木之内氏は、作品に関する「概念」はもちろんのこと、広さや明るさ、天井の高さなどを含めたスケール感が必須だと答えます。また、事前の打ち合わせで大切にしいているのは、デザイナーや設計者、クライアントとの相互理解だと語ります。どのようなプロセスでアートが組み込まれたのかをしっかりと理解し、時間や予算など現実的なプランに落とし込む作業は、図面などのデータだけではなく、対話を重ねることで初めて実現されるそうです。
はやし氏は、どのような環境や場所にプロジェクトがあるのか、アートが具体的にどのような形で求められているかを大切にしているそうです。初対面の人たちと同じプロジェクトを組む場合も、デザイナーが設計者やクライアントと同じコンセプトを持っているかを重視しているとのこと。こうした条件が揃うことで、自身も積極的にプロジェクトに参画できると語ります。
岡林氏は、情報は豊富な方がありがたく、設計図だけでなく使用する素材の実物なども共有してもらうとのこと。相手を喜ばせたい、意外性を出したい、クライアントのイメージを超えた作品を作りたいというモチベーションを持ってプロジェクトに取り組めると、ワクワクしながら制作できると語ります。
KAARA氏は彫刻を手がける関係から、エレベーターのサイズや溶接可能な現場か、壁にアンカーを仕込めることができるのかなどの条件に加え、テーマやコンセプトがあれば十分だと語ります。必要最低限の情報を元に制作しながら、ときには途中経過をプロジェクトメンバーとディスカッションしながら作品を生み出していくそうです。
アーティストとデザイナーの間に立つ藤田氏は、お互いの理解不足によってアーティストと同じプロジェクトに参画することに消極的なデザイナーはまだまだ多いと語ります。尻込みせずに一回本気で一緒に空間を作ってみると、アーティストの考え方や姿勢が理解でき、他のアーティストの考え方も自然と読み解くことができるのではと語ります。藤田氏自身もアーティストとして、デザインとの融合で空間自体の個性を引き立たせるような作品を目指したいと語ります。
ニコラ氏からも、デザイナーもアートの勉強をして、アーティストもインテリアデザインの世界を考えながら、お互いが融合していくべきとの話がありました。空間デザインで100%、アートで100%、合計で200%にすることができる。その融合のためのコミュニケーションが重要だと述べました。
デザイナーとアーティストの相乗効果
最後のトークテーマは、「インテリアデザイナーとアーティストがマッチングするために必要なもの」。
木之内氏は、JCDの会員になったことでインテリアについても学ぶ機会が増えたと言います。例えばJCDの中にアート部門のようなものが新設されたら、デザイナーとアーティストの言語領域も自由に行き来できるようになり、相互理解が一層進むのではないかと語りました。
はやし氏は、今回のトークセッションの開催自体がとても嬉しいことだと語り、満席になった会場を眺めながら、インテリアの中にアートを組み込んだプロジェクトに興味を持つデザイナーが、実は想像よりもたくさんいるのではないかと期待を述べました。
岡林氏は、とにかく人に知ってもらうための活動に注力してきたとのこと。百貨店の個展から始まり、ギャラリーの個展、そして空間の仕事をしていく中で、空間に生きるアートを発表することを心がけているそうです。アートを広く知ってもらうためにデジタル化にも挑戦したいと語ります。
KAARA氏から語られたのは、アーティストのキャリア育成についてです。同じ芸術系大学でもデザイン学科の生徒には出会いの場が数多く用意されていることから、純美術を学んでいる学生やアーティストにもキャリアプランを描けるような場所作りが必要だと力強く語りました。
ニコラ氏は4名の話を総括し、アーティストとデザイナーが歩み寄るための取り組みを作る必要があると語りました。現時点で何が足りないか、何が必要なのかをディスカッションして、今日あげられた課題を解決するようなソリューションを見つけていきたいと述べます。JCDのリーダーシップに期待しながら、今日この会場に集まった全員が同じ方向に向かって考えることで、アイデアの相乗効果が生まれるとセッションをまとめました。
トークイベントの後には交流会が開催され会話を楽しむ姿が見られました。今回印象的だったキーワードは、アーティストとデザイナーの相互理解。プロジェクトへの取り組み方はアーティストごとに三者三様ですが、共通していた点は「対話」です。それぞれのパフォーマンスを最大限に発揮するために、お互いの仕事や姿勢を理解し尊重することが大切だと繰り返し強調されていました。オンラインでのやり取りが主流となり、顔を合わせずとも仕事に取り組むことが当たり前になってきた世の中で、対面でのコミュニケーションが果たす役割を再認識できたイベントでした。
一般社団法人日本商環境デザイン協会(JCD)
この記事に付けられたタグ
関連記事
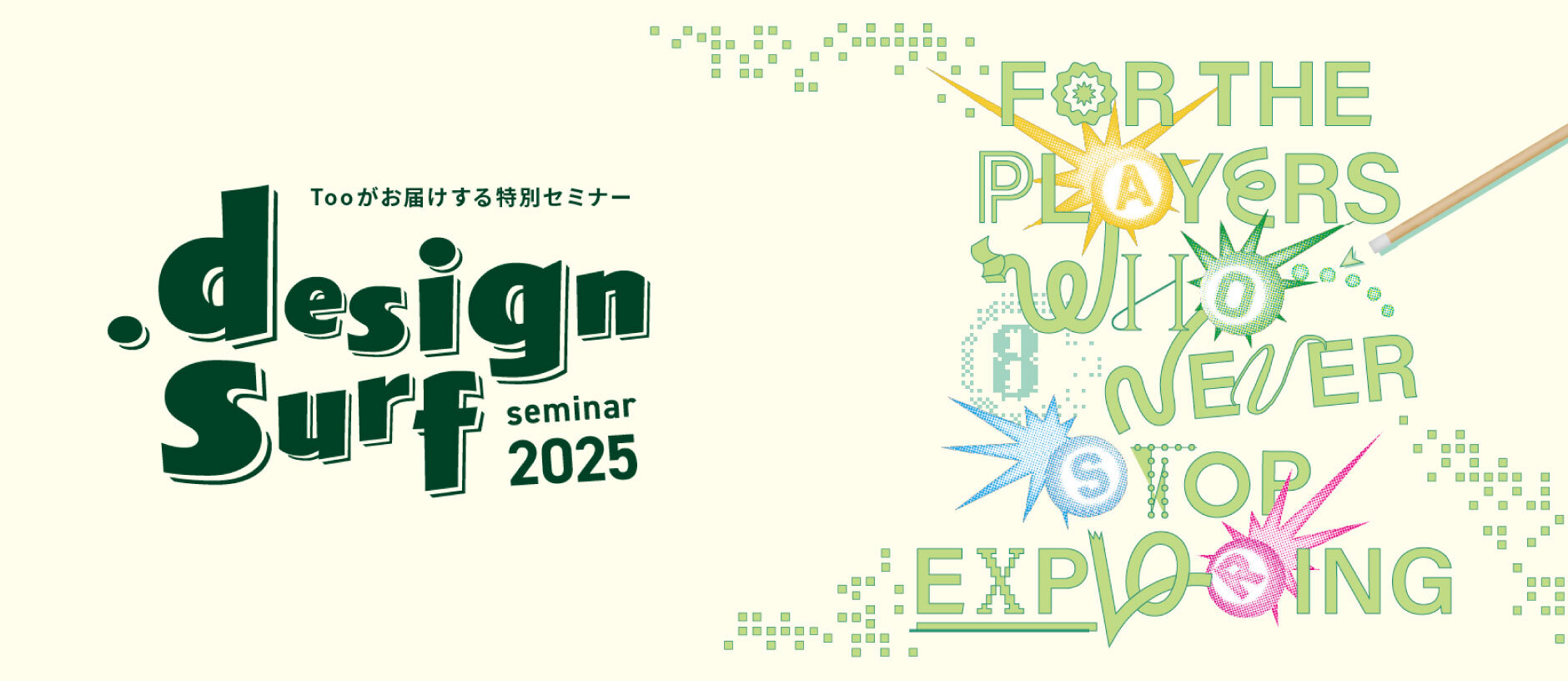
【design surf seminar 2025】design surf seminar 2025 速報
2025.11.10

【現場を変えるMobilityのアイデア】第33話:Apple ID管理の「解」来たる!?
2025.10.27

Designship 2025が開催。デザインと共に歩むパートナーシップの姿勢を発信
2025.10.15

実りの秋に収穫する、最新デザインとビジネスの知見 - design surf seminar 2025 見どころ紹介
2025.09.25

【現場を変えるMobilityのアイデア】第32話:可能性を拡張する問いを立てる力
2025.09.11

パターン作成からモックアップ制作までを内製。効率化されたCMFデザインプロセスを学ぶ
2025.07.23

【現場を変えるMobilityのアイデア】第31話:腹落ち感が生み出す研修の価値
2025.06.10










